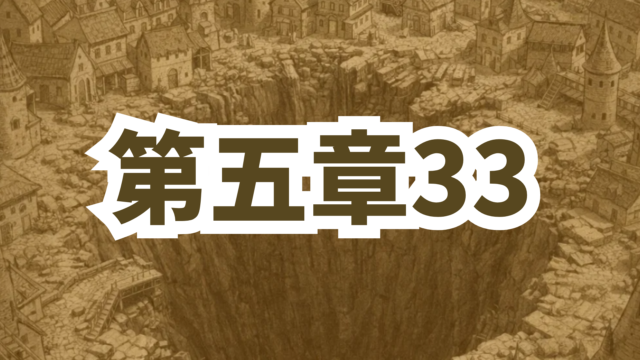アイアイの大冒険 第五章23

大階段を降りるアイルの目線にはあるものが見えてきた。コルヴィンは何かにおびえたようにうつむき足元だけを見ている。
アイルは目線の先、階段を降りた先に、金属の硬い冷たさを感じていた。はじめアイルはそれが何か認識できなかったが、認識できたときには、それの存在を信じたくないと思うようになっていた。
「……コルヴィン…これは…」
大階段の最下部に 重たい鉄格子が降りていた。
まるで地下全体が封鎖されているかのように
びくとも動かなかった。
顔を上げたコルヴィンが青ざめた顔でへなへなと座り込む。
「……あ、あああああっ!そ、そうでした……!緊急時は、地下階層ぜんぶ封鎖されるんでした!!警部の方々くらいしか出入りができません…」
鉄格子の一部には人一人が出入りできそうな扉の部分もあったが、そこにも
鍵がかかっている。
アイルは鉄格子を握って揺らした。
硬い金属音が虚しく響く。

「そんな……!警備室ってのは、この先なんでしょ?!」
コルヴィンは両翼で頭を抱え、泣きそうな声を漏らした。
「む、無理ですよアイルさん……! 封鎖は解除権限が上層部にしかなくて……この出入りの扉も開けられるのは警備部だけです。 わ、わたしが触ったら私もただではすみません!… これは……あきらめて、いったん診断室にね…戻りましょう…よ…」
戻る。
その言葉に、アイルの胸が痛むように跳ねた。
(戻るなんて……できない……!)
たしかに通常は戻るという選択肢もあるのだろうが、今のアイルには考えられないことだった。
そのとき、腕の中のモヤモヤがぴくりと震えた。
「……モヤモヤ?」
返事のかわりに、
モヤモヤはアイルの腕からふわりと浮き上がった。
鉄格子の前まで進むと、
小さな手のような光の突起をそっと金属へ触れさせる。
「……モヤモヤ?どうしたの……?」
コルヴィンは半泣きのまま絶叫した。
「だっ、だめですって!! そんなに触ったら警報が――」
モヤモヤは返事もせず、全身の光をぎゅっと縮めるように集中し始めた。
しん……と空気が固まる。
直後――
カチィィン。
乾いた、しかし深みのある機械音が響いた。
アイルの目が見開かれ、コルヴィンは口を閉じたまま固まった。
鉄格子の扉が、ゆっくりと、開いた。
「……うそ……開いてる……?」

「ひぃぃぃぃぃ!?!?!?え?え?え!?あ、あ、あなたの腕に抱かれているその雲みたいな……も、もしや神族か何かであられ、あられますか!??」
コルヴィンは慌てすぎて翼がパタパタ暴れ、完全に混乱していた。
アイルは鉄格子をくぐりながら、 モヤモヤを胸元に抱き寄せた。
「神族……」
アイルは少し考え、苦く笑う。
「……そうか。あなたたちにとっては“神族”って、本当に神さまみたいな存在なんだよね」
アイルはそっとモヤモヤの頭を撫でた。
「ありがとう、モヤモヤ。やっぱり神族だけあってこのくらいのことはできるんだね。ちょっとチートだけど、 行けるね、これで。ありがとう」
モヤモヤはうれしそうに光を震わせた。
コルヴィンは鉄格子の扉が完全に開いたのを確認すると、
恐怖と驚愕で足を震わせながらも、 アイルの後を追いかけてきた。
「……アイルさん……す、すごい…神族と…お友達?…お友達なんですね!…初めて見ました神族」
アイルは振り返らず答えた。
「…うん。そう。お友達。心強いでしょ?」
地下へ続く階段の先は、 冷えた空気がゆっくりと流れていた。緊張と期待が入り混じる中、 アイルはふたつの影を引き連れ、ゆっくりと地下通路を進んだ。
警備室はもうすぐ近くだ。
カラス族たちの騒がしい声が聞こえてきていた。