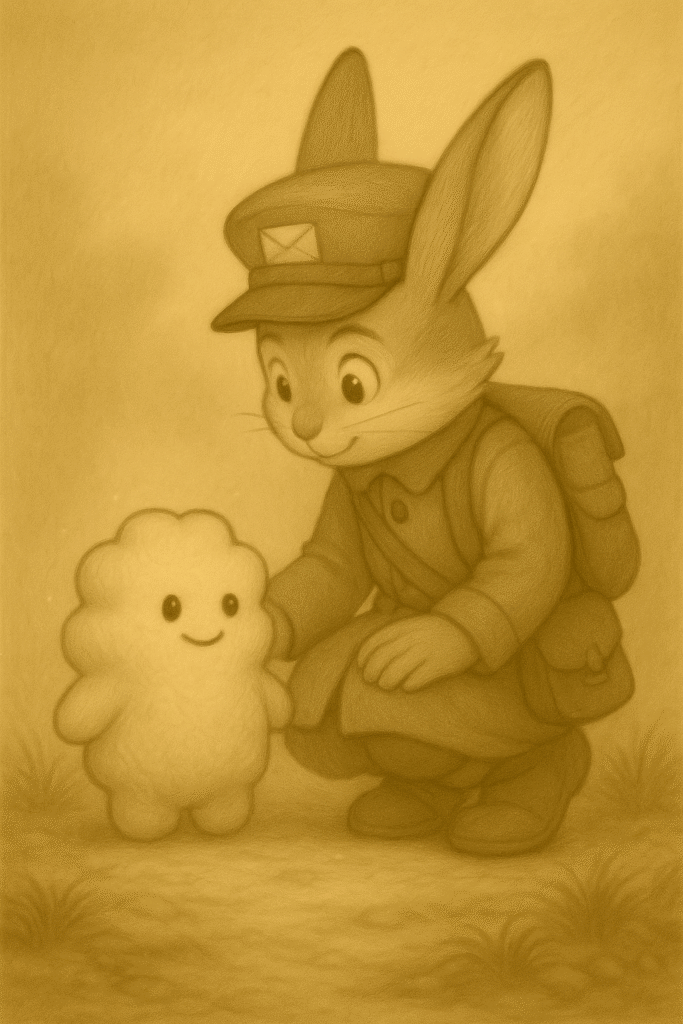
霧はいつの間にか、白から淡い金色に変わっていた。
光の粒が漂い、風もなく、音もない。
まるで世界全体が息を潜めているようだった。
その中心に――それはいた。
幼児ほどの大きさで、輪郭を持たない。
モヤのように揺らめき、時折、光が脈動する。
けれど、その光はどこかあたたかく、見ているだけで胸の奥がふっと軽くなるようだった。
「……かわいい……」
アイルが思わず呟いた。
スペーラーが横で腕を組む。
「“かわいい”……の定義にもよりますが、確かに珍しいですね。触ってもいいんじゃないですか?」
「え、いいの!?」
「え、よくないでしょ!!」
シーカーが慌てて前に出る。
「何かわからないんだぞ!?罠かもしれないし、毒とか出したらどうすんだよ!」
アイルはシーカーの声を聞いていなかった。
そっと、手を伸ばす。
モヤはゆらりと形を変え、指先の動きに合わせて震えた。
そして、ほんの一瞬だけ――指先が光に触れた。
ふっと空気が震える。
アイルの胸の中に、言葉にならない“感情”のようなものが流れ込んできた。
懐かしさ。孤独。安心。
それらが一瞬にして混じり合い、消えた。
「……今、なにか、伝わってきた」
アイルは小さく息を吐いた。
シーカーは顔をしかめる。
「やめとけって……危ないって。そんなのに関わったら、どんな目に合うかもわかんないぞ!神族かもしれないし…」
アイルは首を横に振った。
「違うよ。危険じゃない。なんか――“話したがってる”感じがしたの」
スペーラーはその様子を見て、肩をすくめた。
「ふむ。意思疎通を試みるタイプかもしれませんね。
まあ、持って帰るならお好きにどうぞ。私は興味深いものが見れて満足です。」
そう言って、背伸びをしてあくびをした。
「お、おい!そんな軽く言わないでくださいよ!?」
シーカーが叫ぶが、アイルはもうしゃがみ込んでいた。
モヤはアイルに触れられると、彼女の掌の熱に反応するように光った。
「……ねえ。あなた、名前ある?」
問いかけに、モヤはふるふると揺れた。
まるで“ない”と答えているようだった。
アイルは少し考えて、笑った。
「じゃあ、名前……モヤモヤ、でどう?」
モヤは一度だけ光を強く脈打たせ、アイルの胸元に寄り添った。
「わあ……気に入ってくれたのかな」
「……いやいやいや、なにそのノリ。どうなっても知らないよ!」
シーカーが頭を抱えた。
アイルは立ち上がり、振り向いた。
「ねえ、連れて帰っていいよね?」
スペーラーは視線を空に向けたまま答えた。
「いいんじゃないですか。生き物の飼育は自由です。私は責任を負いませんけど」
「ほら、スペーラーさんも言ってる!」
「いやいやいや! “責任を負わない”って言ってんだよ!?聞けよアイル!!」
だが、アイルはすでにモヤモヤを背中のリュックに入れていた。
モヤモヤの光が布の隙間からほのかに漏れる。

シーカーは天を仰いで、深くため息をついた。
「……わかったよ。落ちるときは一緒に落ちてやる」
「そうこなくっちゃ!」
アイルが笑うと、モヤモヤの体の奥で小さく光が瞬いた。
それが、まるで笑い返したように見えた。
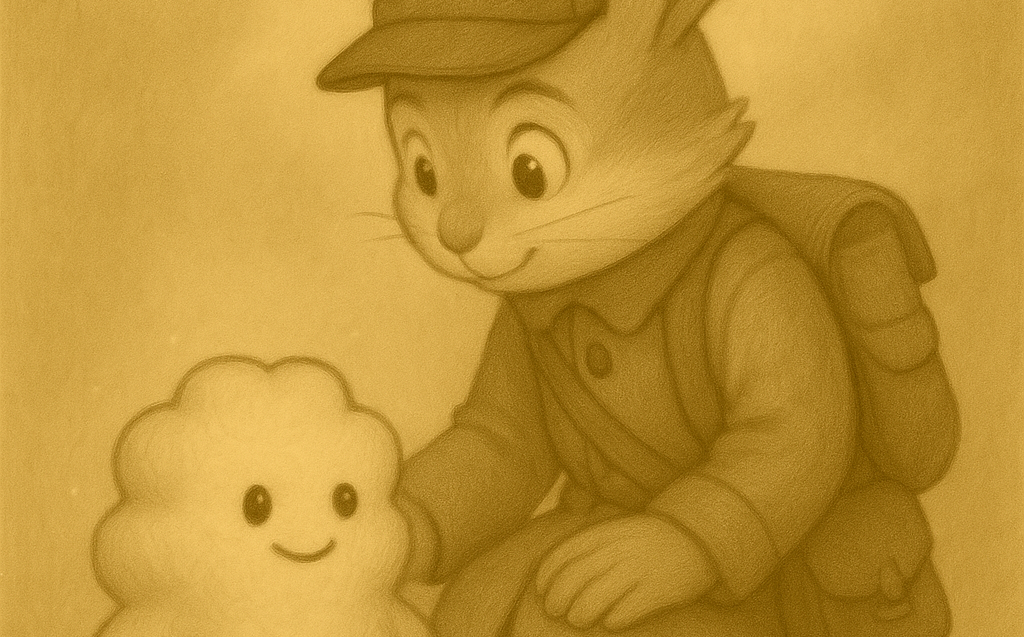


コメント