ふたりはコリク、猫族の使者により、記録室のさらに奥へと導かれた。新たな情報が見つかるかもしれないと王に勧められたのだ。今度はコリクもついてきた。
そこは本来アクセスできない領域──王国内の端末にも接続されていない、隔絶された“記憶の死角”だった。
「ちょっと聞いてもいいですか?」
アイアイは、使者へともコリクとへもとれるとれる声で質問した。
「この城は、どうしてこんなに変・・・なところや、封鎖されているところが多いんですか…」
「変というのは…」
コリクが「変」の定義を問い正そうとする前に使者が答えた。
「ここは、『あのとき』の影響をずいぶん受けているんですよ…歪んでしまったんです…」」
妙な沈黙が流れ、そこからは誰も口を開くことはなかった。『あのとき』の話が出たときには、ほとんどの場合、皆がこの雰囲気を味わってきた。『あのとき』とは、それほど恐ろしいことだったのだ。
先ほどの地下室と全く同じ作りの小さな部屋の中央には、また石の台座があった。その表面には、ひび割れた記録板が埋め込まれていた。
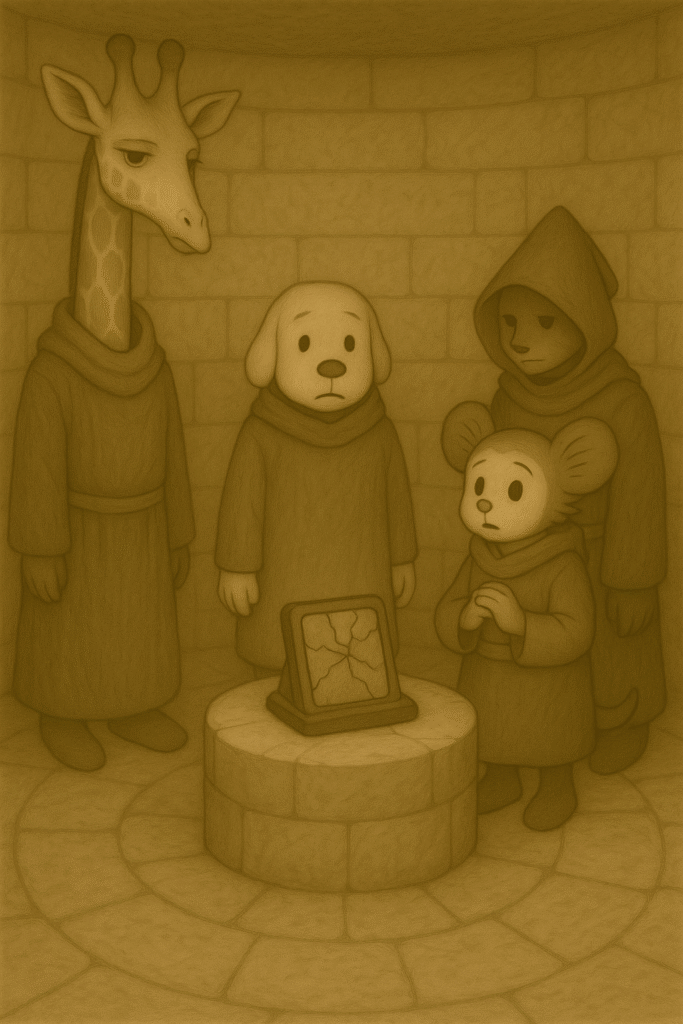
コリクが静かに歩み寄り、それを確認した。
「……これは《AL-09》。本来、すでに抹消されたはずのログです」
アイアイが身を乗り出した。
「何か映るんですか?」
グリグリがふちの突起に気づき、指でそっと押した。かすかな音とともに、台座が淡く光を放ち始めた。
空間に浮かび上がった映像は、粗末な机と紙束、そしてひとりの少女だった。 先程の部屋でも見たあの少女。彼女は何かを書きつけ、震える指で端末に入力をしている。
『……これが最後の操作になるかもしれない。でも……やるしか、ない』
その声は、風のなかに浮かぶ祈りのようだった。
『……これは、あの人のために。もし誰かが、ここにたどり着いたら──』
画面が暗転し、浮かび上がる文字列。
《AL-10:連結済 位置:霧丘外郭、旧塔区域 転送権限者:アイル》
静寂の中、アイアイは胸の奥で何かが脈打つのを感じていた。
「この少女がアイル?……」
「アイルは……母の名です」
アイアイは再びためらわず口にした。
「・・・同一人物とする根拠はなにひとつありません。ありませんが、、」
コリクは今までになくなにか不安そうな顔をしていた。
グリグリは目を伏せたまま、小さくつぶやいた。
「……声、聞いたことがある」
アイアイは混乱したまま言った。 「でも……ぼくたちは、村の人たちを探しに来たはずだよね? トロトロット公国の侵攻のこと、情報はないの?」
その言葉に、コリクが応じた。 「侵攻について、王国の記録には“存在しない”と申し上げました。そのような報告も一切上がってきていません。ですが、この記録は、無関係とは言い切れません」
「どういうことですか……」
「時系列上、あなたが言った村の襲撃の時間とつじつまがあいます。これは推測ですが──誰かが、襲撃から何か、あるいは誰かを守るために、転送を行った可能性はあります。何も根拠はありませんがその可能性はあります。あまり”推測”は好きではないのですが。」
その瞬間、空気が張り詰めた。
グリグリが立ち上がり、まっすぐにコリクを見た。
「そこに行きたい。行かなくちゃいけない気がする」
アイアイも同じ気持ちだった。トロトロット公国に乗り込む、いますぐにでも乗り込む。その思いにアイアイはなんどもさいなまされてきた。そのたびにトロトロット公国に乗り込み、無力の子どもである自分が捕まればそれですべて終わりだと考えて耐えてきた。自分のできること、やれることを積み上げるしかないと考え耐えてきた。
「ぼくら、次の場所──霧丘外郭の“旧塔”ってところに向かいます」
しばらくの沈黙ののち、コリクは静かにうなずいた。グリグリが顔をあげると、フードの隙間から、猫の使者の口角が上がっているのが見えた。
---------------------------------------
翌朝、ふたりは城の裏門から出発する準備を整えていた。猫族の使者はふたたび姿を現し、荷を背負うのを手伝ってくれていた。
空は、鈍い灰色に染まり、遠くの山々には霧が低く垂れこめていた。
出発を前に、もう一度王に挨拶したいと申し出たが、「今朝は“雲のシフォン”が失敗続きで機嫌が悪いらしい」とのことで、代わりにコリクが現れた。
「本来、この道は開放されていません。ですが、王の許可があるのならば通行は妨げません」
コリクは相変わらず無表情だったが、その言葉の端々に、どこか親しみのような、言葉にならない温度があった。
「転送記録の末尾に示された“霧丘外郭”(むきゅうがいかく)。そこは、ザラーリンの行政管理外に位置しています。正式な地図には記載がなく、行き方を記録した者もわずかです」
アイアイは頷いた。
「でも、そこに行かなきゃいけない気がするんです。アイルに──に会えるかもしれない」
コリクはふと目を細めた。
「“会う”という動機に、合理性はありません。しかし……感情には、時に道を切り拓く力がある…のかもしれません」
アイアイはコリクの目をまっすぐに見つめて言った。
「ありがとう」
グリグリも黙ってうなずいた。猫族の使者は最後まで何も言わず、準備を続けていた。驚いたことに猫の使者もつ霧丘外郭へついてきてくれることになっているらしかった。
城を背にして、ふたりは坂を下り、いつの間にか城のふもとまで届いた霧のなかへと足を踏み出した。猫の使者はふたりの後ろを黙ってついて歩いていた。
”霧丘外郭”に何があるのだろうか。村では聞いたことない場所だった。
不安とともに、一人で旅に出た自分に、今二人の「道連れ」がいることが心強くも感じた。
──ふと、後ろの使者がつぶやいた。
「霧丘外郭か、、あそこは…ドラゴンが出ますね…」
アイアイとグリグリは顔を見合わせてて、息をのみ、グリグリは顏を真っ青にして、踵を返し城へ戻ろうとした。アイアイは何とか裾をつかんでグリグリを止め、何も言わずふたりは、また歩き始めた。
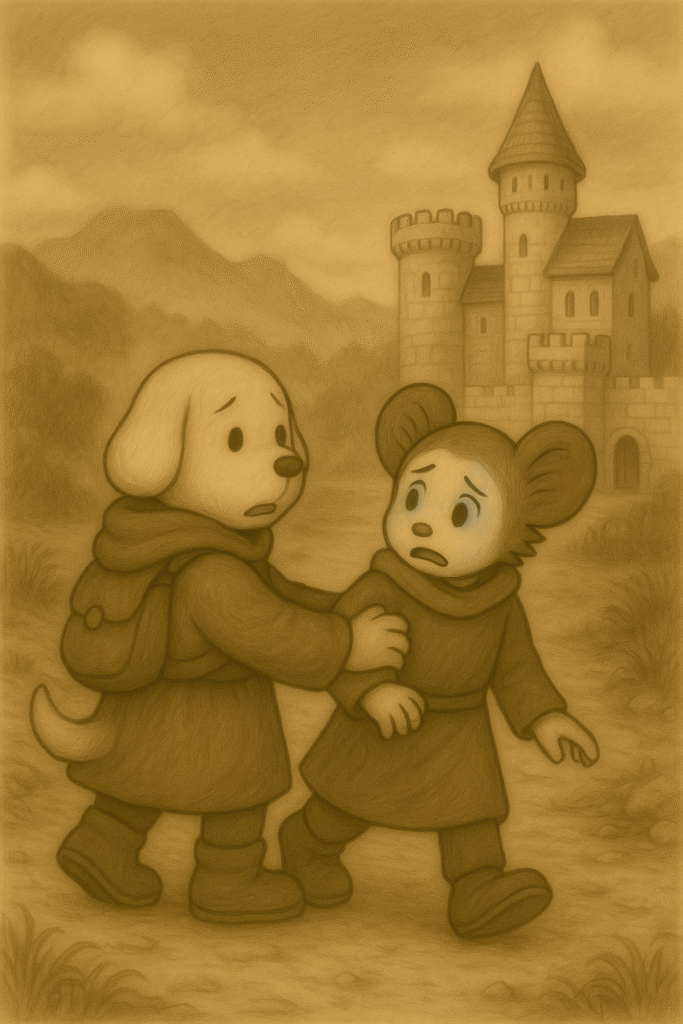



コメント